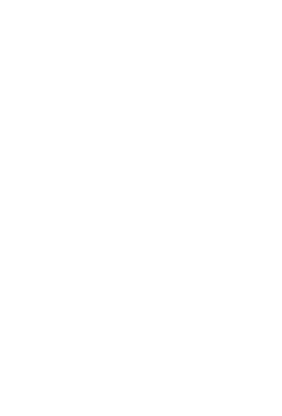About 私たちについて
Purpose / Value
私たちの存在価値と
大切にする価値観
大切にする価値観
育ちあえる未来を、
仕事として実装する。
仕組みにする
すべての存在が“育ち合える”関係性を、社会の仕組みとして実装する。
手応えをつくる
社会とつながっている”という実感のある仕事を設計する。
社会に実装する
地域・企業・次の世代へと、ひらかれたかたちで展開していく。
Message
代表メッセージ
―― 里海珊瑚プロジェクトにつながる、障がい者の活躍への想い
20数年前、インターネットの黎明期に起業し、グローバルなオンラインコミュニティの構築に挑戦してきた私にとって、誹謗中傷や揚げ足取りな風潮にならない「尊重し合う、支え合う、助け合う場を生み出す」、「人と人をつなげる」というテーマは、私の起業家人生の中で一貫して大切にしてきた価値観でした。
かつての起業当初は、ITの力で社会の混沌を少しでも良い方向に動かせるのではないか、という希望を持っていました。中でも、オンラインのゲームや仮想空間を通じて人々が他者と助け合い、感謝され、評価されるような世界観をどうつくるか、そういった実験的な営みが、現在の事業のベースにもなっています。
一方で、実際の社会には、働きたくても働けない人たち、評価される機会すら得られていない人たちがたくさんいます。とくにオンラインコミュニティ空間にて、精神疾患や引きこもり、身体の不自由などを背景に社会との接点を持ちにくい方々とも長年関わってきた中で、現実の世界で抱えるハンディキャップやコンプレックスを超えた自分らしさを表現している様を幾度となく感じてきたことで、「この人たちがもっと活躍できる場をつくりたい」という気持ちが、私の根底に根付きました。
それが障がい者の活躍となる支援への想いの原点であり、その延長線上にあるのが、里海珊瑚プロジェクトです。
――サンゴの保全・再生への挑戦
沖縄県のSDGsパートナー企業として地域での活動にも取り組む中で、また、わたし自身がダイバーでもあり海中のサンゴの白化を目の当たりにすることもあり、海の豊かさを守る活動への関心が高まりました。
海の生態系の中心を担うサンゴは今世紀中に絶滅するとも言われており、全世界的にサンゴの白化現象は顕在化しています。
沖縄近海は世界有数のサンゴの生殖域でもあり、私たちの島のサンゴの保全・再生をするために、「ITx福祉」をテーマとした私たちの独自な取り組みとして、障がい者の活躍とデジタルの活用によりサンゴの陸上養殖・海中植付けを行う「里海珊瑚プロジェクト」の挑戦をスタートしました。
サンゴの保全・再生を深めていくことと共に、この活動を広く周知することで、関わる方々の意識や行動の変容につなげていくことも目的としています。
―― もうひとつの挑戦
里海珊瑚プロジェクトの母体および推進企業であり、「ITx福祉」をテーマとし、障がい者の就労支援を軸とするサンクスラボ株式会社(沖縄県那覇市)では、ITスキルやデジタルワークを通じて障がい者の成長を支援してきました。けれど、デジタルワークということで対象は比較的軽度な精神の障がいのある方々が中心となっており、知的障がい、自閉症、ダウン症をはじめ中度または重度と捉えられ、より手厚い支援が必要な層すべてを包括できているわけではありません。
また、企業側のニーズとしても、障がい者雇用の文脈においては「法令順守のための障がい者雇用ではなく、障がい者雇用が企業の成長や責任と重なる価値をどう設計できるか」という視点が求められるようになってきています。
そうした中で立ち上げたのが、「ITと福祉と環境」を掛け合わせたこのプロジェクトです。
里海珊瑚プロジェクトでは、サンゴを保全・再生する過程そのものが障がい者の“仕事”になります。障がい者が、水槽の管理やサンゴの飼育、観察やデータ記録などに関わりながら、アクアリウムセラピーの効果も体感しながら、自分の役割を果たし、社会と接続されていく。
この仕組みは、企業にとっても「海の再生」、「生物多様性」、「ESG実践」といった文脈で企業活動と接続しやすく、双方にとって持続可能な構造を実現できます。
ITの活用により、福祉の枠を越えて、環境の課題に挑みながら、そこに“働く意味”や“やりがい”を創出する。 サンクスラボの延長線上にあるけれど、決して単なる派生ではない、里海珊瑚プロジェクト株式会社は新たな領域への挑戦です。
―― ソーシャルグッドは、稼ぐことと矛盾しない
このプロジェクトを事業化していくうえで、私が大切にしていることがあります。
それは、ソーシャルグッド、「社会や地球に良いことをすること」と「経済的に稼ぐこと」は、決して矛盾しないという考え方です。
多くのソーシャルグッドなビジネスは、どこかで寄付や無償性を前提とすることで、継続が難しく精神的にも疲弊しやすくなります。
けれど、関わる人々それぞれが、きちんと仕組みとして“稼げる”ように設計することで、社会に対するインパクトははるかに持続的になる。
そして関わる人たちが社会にも地球にも良い、同時に自分たちの収入などにも良いと感じられることで、はじめて安心した充足感や心の豊かさとも言える精神性を高めることができ、それにより関わる人たちの活力が漲る好循環となる。
私はそう信じており、里海珊瑚プロジェクトを通じて、関わる企業の収益や価値向上、障がいのある方々の雇用創出や賃金向上、活動地域の経済活性も実践します。
プロセスエコノミー(Process Economy)という言葉があるように、里海珊瑚プロジェクトは、サンゴの養殖や移植による保全や再生という“成果”だけではなく、そこに関わる人・企業・社会の“プロセス”そのものに価値を見出せる仕組みです。
プロセス自体が経済活動になるように設計する。そこで育まれる連鎖が、未来にレバレッジをかけていく。
それがこのプロジェクトの根底にある哲学でもあります。
―― 誰にとっての価値か?
このプロジェクトの価値は、関わる人の数だけあると思っています。
例えば、観光で沖縄を訪れる多くの人にとっては、海の美しさの裏にある課題を知り、「何かしたい」という気づきにつながる場。 企業にとっては、障がい者雇用・環境・観光の複合的な文脈でESGを実践できる、新たなパートナーシップの可能性。地域の方にとっては、陸上および海中での活動を周知し関心を促すミュージアム、関係する企業によるワークショップやワーケーションでの活用など、新たな観光資源の創出。 そして、就労が困難な障がい者にとっては、自分の役割を持ち、社会と接続される“仕事の場”。
この「誰にとっても意味のある場所」であることが、里海珊瑚プロジェクトの価値であり、強さだと考えています。
―― 未来に向けた次の一歩
現在、陸上および海中でのデジタル活用の実装、陸上でのサンゴ養殖、IoT水槽の管理、モニタリングの仕組みといった実験的な環境が構築できてきています。
今後は、これらの環境だからこそ挑戦できる、海の生態系の中心とも言われるサンゴの生育研究を深めていきます。
減っていくサンゴよりも早く育つ、水温上昇しても元気に生きるサンゴ、その海に本来あるサンゴの生態系を陸上で増やしながら保存する、海中の観察により効果的に再生できるサンゴの居場所を探索等、人手を介した里海ならではの研究により未来への突破口を見出したいです。
またこれらを観光資源としても活用し、より多くの人に開かれた場にしていく計画です。例えば、那覇の国際通り付近に設置する予定のサンゴ保全のミュージアムのような施設では、単なる展示ではなく、海の声なき声や、見えない課題に触れられるような体験を提供したいと考えています。
さらに、これまで主に精神障がい者を対象としてきた支援の枠を広げ、知的障がいや重度な障がいを抱える方々にも開かれたプロジェクトとして設計していくこと。
そして、多くの企業・自治体とともに、ネイチャーポジティブ、生物多様性、ブルーカーボン、地域循環など、より広い社会課題へとこの仕組みを接続していくこと。
世界のサンゴ礁の80%に白化現象が顕在化、最悪の状態とも言われており、沖縄で培う里海珊瑚プロジェクトの幅広いノウハウや実績が、沖縄だけでなく国内外のサンゴ生殖域に貢献し、そこで関わる人々の役に立つこと。
私たちのこれからのチャレンジです。
―― 私たちが目指す未来
この里海珊瑚プロジェクトを通じて、私たちが目指しているのは「海と人と社会が、育ち合える未来を、仕事として実装する」ことです。
働くことが、誰かにとっての救いになり、企業にとっての未来をつくり、海にとっての再生になる。
そんな循環が、しっかりと仕組みとして回り始めたとき、きっと社会は、少しずつ優しく変わっていくのではないか。
それを信じて、私たちは今日もこの活動を続けています。

里海珊瑚プロジェクト株式会社
代表取締役社長
村上タクオ
Takuo Murakami
Company Profile
会社概要
里海珊瑚プロジェクト
株式会社
- サンゴ礁の保全・再生活動に関する企画・研究・運営
- 環境教育・啓発活動の企画および実施
- 地域社会と連携した持続可能な社会モデルの構築